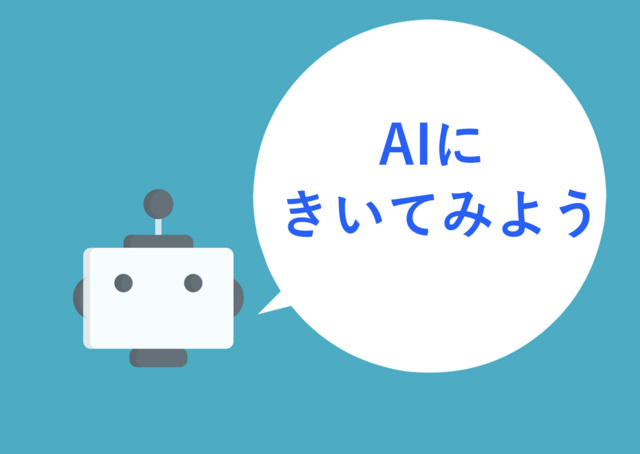──Uさんが「市民」という点を重視するのはなぜですか。
私のように「市民」という立場でゼミに出ていると、「学問は学者がやっていればいい、と思われてはいけない」と感じます。
原発であれ、水俣病などの公害問題であれ、当事者であり、大多数の側でもある市民が動かないと社会は変わらない、動かないです。
もっとも「社会をよくするために市民全員が社会運動をする必要がある」と言いたいわけではないですが。
──市民は社会運動をしたりニュースをチェックしたりするだけでなく、ほかならぬ学問をするとよいと考えているのですね。
ええ、過去の事例や似た事例を学ぶことは学問を通してしかできません。
それから、話が変わるようですが、日本社会を考察した学者として阿部謹也や中根千枝、山本七平がいますね。ある時、もう退任されたS先生と話していて、
「阿部謹也は『世間』について論じているのに、阿部謹也自身は世間から関係ないみたいなところがありませんか」と言ったら、先生は「まるで二階から見下ろしているかのようだ」と笑って答えてくれました。
──なるほど、日本社会を論じた代表的な学者が市民の目線で学問していないわけですね。学者と市民の間に溝ができてしまっていると。
そうです。
他方で、私の好きな、きだみのるは村社会に実際に入っていく。それで村八分にあう。そうして書かれた『気違い部落周游紀行』は有名になった。
* きだみのるは文筆家、翻訳者。フランス留学の経験をもち、民俗学的な著作で有名になった。
きだは阿部謹也らとは対照的だと思う。
「一階」のひとです。ファーブル昆虫記を翻訳してもいますし、開高健とも仲が良かった。留学先のフランスではマルセル・モースに教わっている。モースの『贈与論』なんかド専門じゃないですか。私のバックボーンはきだみのるです。

──そうした学びの背景があるからこそ、学問は市民とともにあってほしいと考えるわけですね。
ええ。
社会問題についてはとくに市民の立場は重要じゃないですか。新聞を読んでいても、学者や行政ではなく、被害にあった当事者、地域の市民がまさに「専門家」であるということはよくあります。
──そうおっしゃる時の「専門家」というのは、学者としての専門家に限定しない意味ですね。たとえば、石牟礼道子さんのようなひとも含まれますか。
『苦海浄土』ですね。文学には文学における共有のしやすさがある。必ずしも学問でなくてもいい。演劇や美術という方法だってある。
* 『苦海浄土』は石牟礼道子の小説。水俣病を扱い、ドキュメンタリーの側面と詩的な感性を融和させた作品。
私がいま言った「専門家」というのは、経験の蓄積があり、近くでつぶさに見てきたひと。
また、当事者であるようなひとです。経験と知識を総合することができて、発信力をもち、社会に還元できれば、それは立派な「専門家」です。
──「市民としての専門家」ですね。
もともと市民は立場や経験、障害、災害や公害で受けた被害などについて多様性がある。
この多様性が大事です。学者任せ、行政任せではなく。いろんな立場やバックグラウンドを活かした発信がなされるのがよいと思います。
──Uさんの「学問」に対する考え方は常に現実と結びついていますね。
学問はともすると現実から遊離する。
学生にありがちなのは、本の一節を引用したりしても、それが現実の問題に適用できていないということ。たとえば、「ドゥルーズが欲望する機械という言葉を使う」と言えても、その概念を現実に適用することはできない。
それでは知識にもなっていない。これは他人を見て批判したくなるというより、私自身がかつてそういう誤りをしてきて、いまも難しいと感じるということです。
ちなみに、私の卒論のテーマは「ひとにものをもらったら、なぜ返さなければならないのか」でした。
実際に私は「互酬関係」が嫌いなので、学生にプレゼントする時も「贈られても返すんじゃねーぞ」と言っています。
* 互酬関係とは、ものを贈られたら等しい価値のあるものを返す、という社会的な関係。阿部謹也は『「世間」とは何か』のなかで互酬関係についても分析している。
自分が学問して得たことを人生に活かして幸せになろうとしているのでしょう。
文・写真:木村洋平
こちらの記事もおすすめ