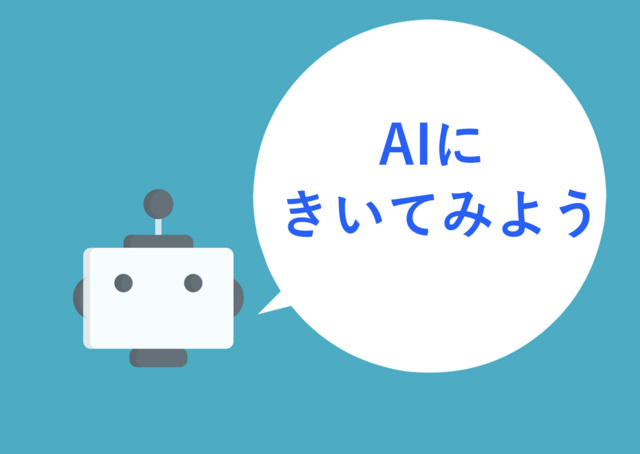カンボジア旅行記。なにげない日常の風景で、食や教育、通貨に注目した時、目の前の食事を大切にすることや、誰かの話をしっかりと聞くことの大切さに気づきます。小さなことからエシカルライフは実践できます。

筆者は旅行でカンボジアとマレーシアを訪ねました。この記事では食文化・教育・通貨の視点から現地の生活を振り返りました。旅先で感じた“エシカルな暮らしのヒント”をお届けします。
東南アジアの国であるカンボジア
6月中旬、私はマレーシアを経由してカンボジアへ旅に行きました。
カンボジアとマレーシア。どちらも東南アジアにある国で、日本から飛行機でおよそ5〜7時間ほどの場所にあります。日本との時差はカンボジアが−2時間、マレーシアが−1時間です。
まずは、筆者が初めてカンボジアを訪ねて感じた印象について説明します。
カンボジアといえば、観光都市であるシェムリアップにある世界遺産のアンコールワットとその遺跡群が有名です。シェムリアップ市内の街並みは、遺跡群と現代の暮らしが混ざり合って独特の雰囲気でしたが、どこか懐かしさも感じられました。

四輪車よりもバイクや自転車の利用率が高く、空港から市内へ向かうワゴン車の車内からは、その車の横を、荷物を載せて懸命に走る人々の姿が目に入りました。バイクは2〜4人乗りが当たり前です。日本で見かける原付から普通二輪程度のサイズのバイクに大人や子どもが4人で乗っています。

一方、マレーシアは多民族国家として知られ、首都のクアラルンプールでは近代的なビル群と、屋台街や市場のにぎわいが共存しています。街を行き交う人々は、マレー系・中華系・インド系などさまざまで多民族国家であることを肌で感じました。
旅の中で印象に残ったのは有名な観光地よりも、もっとささやかな日常の風景や現地の人々との会話です。
食べることや学ぶこと、お金を使うこと。旅のなかでそんなささいな日常に、エシカルライフやサスティナブルのヒントが隠れているように思えました。
「もったいない」の考え方はカンボジアにもある

この写真は、カンボジア・モンドルキリ州にある市場です。市場を歩いたとき、まず目に飛び込んできたのは大きな魚や鶏が無造作に並ぶ屋台、そのとなりで香草やスパイスを売る現地の人たちの姿でした。
市場では、女性たちが慣れた手つきで食材や料理を売り、おつりを渡しながら笑顔で声をかけています。そうしたなにげないやりとりの中に、カンボジアの人々の日常の温かさを感じました。
そして滞在中もうひとつ心に残ったのは、現地を案内してくれたガイドさんに、朝・昼・晩の食事をともにするなかで「残さずたくさん食べてね」という言葉を何度もかけられたことです。
その響きに日本の「もったいない」という価値観を感じ、カンボジア人に親しみを覚えました。
でもそれは単なる習慣ではなく、かぎられた資源や食材を大切に使うという意識が、暮らしの中にしっかり根づいているからこそなのだと気づきました。
旅を通じて感じたのは、「何を食べるか」というより、「どう食べるか」が日々の営みをかたちづくっているということです。日本では当たり前に感じる食事も、宗教や気候、歴史によってさまざまな形があり、それぞれに理由や意味があるのだと気づかされました。
小さな教室で見つけた学びの光

カンボジア滞在中、シェムリアップ州とモンドルキリ州の教育局を訪ね、現地の小学校の先生方と直接言葉を交わす機会がありました。
木造の校舎や風が通り抜ける教室、壁にはられた手描きの教材。そのひとつひとつに、子どもたちに学ぶ楽しさを伝えようとする先生たちの工夫と想いが感じられました。
先生方が話してくれたのは、カンボジアの農村部には学校へ行きたくても行けない子どもたちがいること、国全体で教員や文房具、校舎そのものが足りないという現実です。
そして、カンボジアでは日本と異なり、授業が午前か午後のどちらか半日しかないということも教えてくれました。その理由は、多くの子どもたちが家の手伝いをしているためです。
それでも「学びたい」と願う子どもたちがいるから、自分たちはあきらめずに教え続けるのだと語る先生の瞳は、とてもまっすぐで力強いものでした。
日本では環境の整った教室や十分な教材で学ぶことが当たり前で、それを当然と思っている自分がいます。たとえば、日本では子どもたちひとりひとりがタブレットやPCなどを持っており、授業で活用されていますが、カンボジアの公立学校ではデジタルデバイスは一切利用されていませんでした。
でも旅を通じて感じたのは、目を輝かせて学ぶ子どもたちを見て、「学ぶ」というのはただ知識を得ることではなく、「知りたい」「学びたい」と願うその気持ちこそが未来をつくるということでした。そしてそれは、私たち大人にとっても変わらないのだと思います。
カンボジア通貨「リエル」が教えてくれたこと

カンボジアを旅して最も印象に残ったのはお金の使われ方でした。
カンボジアは米ドルと現地通貨である「リエル」が併用されていて、支払いはどちらの通貨でもできます。クレジットカードに対応しているお店は少なく、米ドルで支払うとおつりはリエルの紙幣で返ってくるのが当たり前でした。
街中ではQRコードを使った電子決済「ABA PAY」も見かけましたが、利用している人はそれほど多くないように感じました。
リエルは紙質が柔らかく、色とりどりで、日本のお札とはまったく違う温かみがあります。
薬局で塗り薬を買ったときのことです。リエル紙幣を数えるのに苦戦していると、店員のお姉さんが「合っているよ」と笑いかけてくれ、ほっとしたことを今でも覚えています。
お札を数える手元はとても丁寧で、紙幣は少しくたびれていても大切に扱われていることが伝わってきました。
何度も現金でやり取りをするうちに、「必要な分だけを使う」という感覚が、人々の暮らしの中に自然と息づいているのだと感じました。
キャッシュレス決済やクレジットカードでの決済に慣れた自分にとって、お札を一枚ずつ数えながら「今日はどれだけ使えるかな」と考える時間は、とても人間らしくて豊かなことなのかもしれないというふうに思いました。
まとめ:小さな問いから始まるわたしのエシカル

旅の中で心に残ったのは有名な観光地よりも、ふと目にした市場の風景や、交わした小さな会話でした。
「異なる文化に触れた」というよりも、“こんな生き方もあるんだ”という、ささやかな発見の連続だったように思います。
カンボジアやマレーシアの人たちの暮らしぶりを見て、なにかを知って学んだというよりも、「わたしならどうするだろう?」という小さな問いが芽生えました。
きっと今すぐ大きなことはできなくても、毎日の食事をきちんと味わうこと、誰かの言葉にちゃんと耳を傾けること。そんな一歩ずつの行動からでも、エシカルライフは始められるのかもしれません。
文:すぎやまゆい
写真:©2025 Ryota Toyonaga