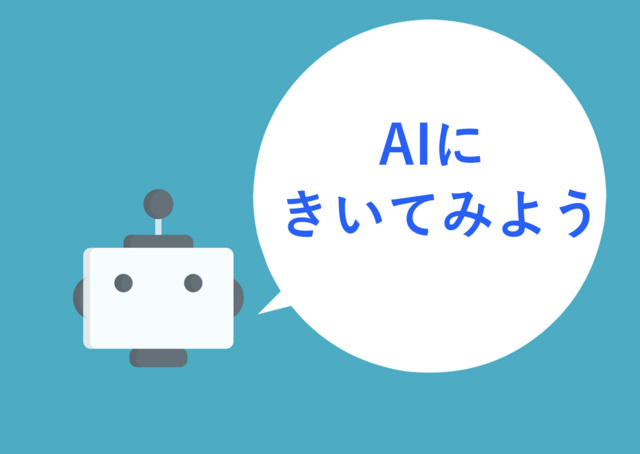スーパーや道の駅でたけのこを見ると、春の訪れを感じます。たけのこのアク抜き(下処理)の方法や、シンプルな材料で作る「たけのこご飯」の作り方を紹介します。
3月から5月が旬のたけのこ
たけのこは竹の若芽ですが、成長がはやく、すぐに竹になってしまうため、限られた時期しか食べられない食材です。
たけのこには種類があります。スーパーなどでよく見かけるたけのこは「モウソウチク(孟宗竹)」という種類で、3月〜5月が旬です。皮に黒い斑点があり、強いアクが特徴の「マダケ(真竹)」や淡白でアクが少ない「ハチク(淡竹)」などもあります。
春は苦味のある食材を食べるとよいと言われます。「春の皿には苦味を盛れ」ということわざをご存じですか?冬の体は新陳代謝を抑え、体内に栄養を蓄えて、寒さに耐えようとします。そして春の体に切り替えるのによいといわれるのが苦味です。苦味にはデトックス効果があります。このことわざは、苦味やえぐみが多いたけのこや山菜を食べて、体内をリセットしようという昔からの知恵なんですね。
では、たけのこのアク抜きのやり方とたけのこご飯の炊き方を紹介します。
たけのこのアク抜き(下処理)の方法
たけのこは収穫直後からアクが増えます。そのため、すぐにアク抜きします。可能なら、買った当日に処理してしまうのがよいでしょう。
たけのこのアク抜き(下処理)に必要な材料は、たけのこ、米ぬか(たけのこの重量の約1割)です。米ぬかは、玄米の表面を削って精米する際に出る粉です。
- 外側の皮を2〜3枚むきます。根本の固い部分と穂先を3cmほど切り落とし、縦に2〜3cmの深さの切り込みをいれます。
- たけのこを鍋に入れ、たけのこがかぶるくらいの水を入れます。そこに米ぬかを入れ、強火にかけます。
- 沸騰したら落としぶたをして、弱火で約40分〜1時間ほどゆでます。
- たけのこの根元に串をさし、スッとささるようになったら、火を止めます。湯切りはせず、たけのこが冷めるまでそのままに。
- たけのこが完全に冷めたらお湯を捨て、水で洗って皮をむきましょう。
米ぬかはスーパーやお米屋さんで購入できます。米ぬかが手に入らないときは、お米(ひとつかみ、無洗米NG)やお米のとぎ汁でも代用可能です。
参考:農林水産省「これからが旬!たけのこで「春」を感じよう」
「たけのこの炊き込みご飯」の作り方

炊飯器で簡単に作れる、たけのこの炊き込みご飯を紹介します。
材料は、米(2合)、アク抜き済みのたけのこ(150g〜200g)、油揚げ(1枚)、だし汁(約300ml)、醤油(大さじ2)、みりん(大さじ2)、塩(小さじ¼)です。
- お米は30分〜1時間ほど浸水させます。
- たけのこをくし切りに、油揚げは短冊切りにします。
- 材料をすべて入れ、炊飯器の普通モードで炊きます。
- 炊き上がったら混ぜ合わせて完成です。
お好みで牛肉やにんじんを入れてもおいしいです。
参考:白ごはん.com「たけのこご飯(炊き込みご飯)のレシピ/作り方」
まとめ
たけのこは、煮ても揚げても焼いてもおいしい食材。日本食との相性がよく、さまざまな食材に合います。スーパーや道の駅などで、新鮮なたけのこを見つけたら、アク抜きから挑戦してみてはいかかでしょうか。春の訪れを台所で感じてみるのもよいかもしれません。
文:古賀瞳